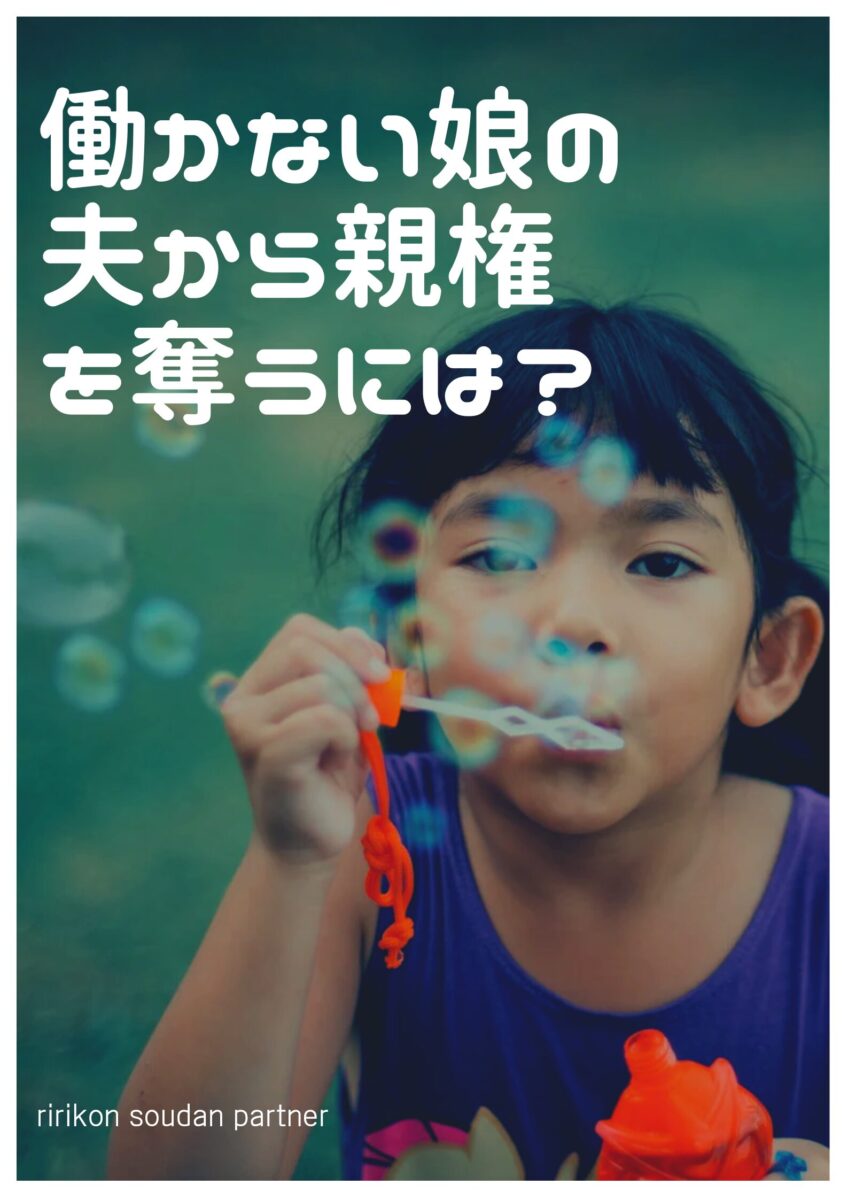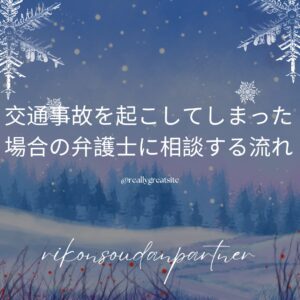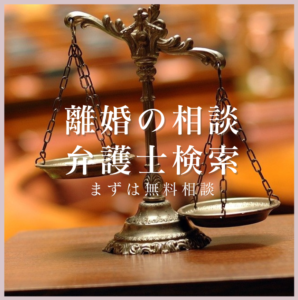相談ケース
娘が死亡し、娘の夫が親権者として9歳の孫と二人で生活していますが、娘の夫はろくに働かず、ギャンブルばかりしているようです。このままでは孫の教育上よくないので、娘の夫から親権を取り上げて、祖母である私が孫の面倒をみたいと考えているのですが、そのようなことは法律上可能でしょうか。
回答例
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるとき、その他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより、子の利益を著しく害するときは、子の親族などが家庭裁判所に親権喪失の審判を申し立てることができます。
そこまで至らない場合でも、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより、子の利益を害するときは、家庭裁判所に親権停止の審判を申し立てることができます。
育児放棄もこれらの要件に該当する可能性があります。
解説
民法では、第4編、第4章に「親権」の章を置き、未成年の子に対する親権について規律しています。
親権は、父母の子に対する監護教育の権利義務の総称で、その効力は、子の身上に関する権利義務と子の財産についての権利義務の双方に及びます。具体的に民法が規定する親権の内容は、監護教育権(民820)、居所指定権(民82)、職業許可権(民823)、財産管理権(民824)、一定の身分上の行為についての代理権(民797①)、子の人格の尊重(民821)などです。
親権は、父母が婚姻中は父母が共同して行いますが(民818③本文。親権共同行使の原則)、父母が離婚する際には、協議離婚であっても裁判離婚であっても、父母の一方を親権者と定めなければなりません(単独親権)。すなわち、協議離婚に際しては、協議で父母の一方を親権者と定める必要があります(民819①)。離婚の合意ができても、親権者の指定について協議が調わないときは、離婚届を提出しても受理されません。そのため、離婚の合意ができていても、親権者の指定の合意ができない場合には、調停、審判、裁判で定めることになります。裁判離婚の場合は、裁判所が父母の一方を親権者と定めます(民819②)。裁判所は、諸般の事情を総合的に考慮して親権者を定めますが、その際の主な考慮要素としては、以下のものなどがあります。
① 主たる監護者
これまで子の監護を主に担ってきた親(主たる監護者)は、離婚後も子と暮らすことが子の福祉に沿うので、親権者に指定される傾向にあります。
② 監護の継続性
生活の変化は、不安や混乱を招くので、出来るだけ避けるべきであるから、現状の監護を継続すべきであるという視点が考慮要素となります。
③ 監護の態勢・環境
監護の態勢・環境が整っていることが、親権者の指定に有利に働きます。親権者自身が子の監護に十分な時間を割くことができない場合には、監護補助者の存在が重要となります。また、親の経済状況や住環境等も考慮要素となります。
④ 監護能力
親の心身の健康状態や、これまでの育児における問題も考慮要素となります。もしこれらについてマイナスの要素がある場合には、その対策が講じられているか否かが鍵となります。
⑤ 子の意思
子が15歳以上のときは、親権者を定めるに当たって、子の陳述聴取が必要とされているように(人訴32④等)、子の意思は大きな影響を及ぼす判断要素です。子の意思の把握については、実務上、家庭裁判所調査官が重要な役割を担っています(家事手続65等)。裁判上の和解による離婚(人訴37)の場合も、審判離婚(家事手続284)についても同様です。調停離婚においても、離婚の調停を成立させる場合にも、原則として親権者を指定します。なお、父母の一方が死亡した場合には、他方が当然に単独親権者となります。
親権は、親の利益のためにあるものではなく、子の福祉を目的とするものですから、親権者の親権の行使が不適切で、子の福祉を害するときには、親権を失わせる必要がある場合もありますが、他方では、親権が義務であることを考えれば、安易に親権を喪失させることも適当ではありません。
そこで、民法834条は、「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」は、家庭裁判所が、親族等の申立てにより親権喪失の審判をすることができる旨を規定しています(家事手続別表第1)。
従前は、親権の行使が不適切である場合の対処方法としては、親権喪失という重大な効果を生じさせる制度しか存在しなかったため、柔軟に対応することができませんでした。そこで、平成23年に民法が改正され、新たに親権停止の制度が設けられました。すなわち、民法834条の2第1項は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であ
ることにより子の利益を害するとき」は、家庭裁判所が、親族等の申立てにより親権停止の審判をすることができる旨を規定しています(家事手続別表第1)。家庭裁判所は、「親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」、2年以内の親権停止期間を定めます(民834の2②)。
判例
○親権者の父が妻以外の女性と情交関係を持ち、同棲したことは道徳的非難を受けるとしても、直ちに子の監護教育に不適任であるとはいえないとして、親権の喪失が認められなかった事例。
(高松高決昭43・11・5判タ239・302)
○夫が死亡後、子らを祖父のもとにおいたまま他の男性と婚姻した母について、親権の喪失が申し立てられた事案につき、他の男性と情交関係を継続したことによって子らの心身の健全な育成が妨げられたとは認められないこと、母と子らと別居させ、親権を事実上行使し得なくなったのは、親族の圧力によるものと認められることなどの理由から申立てを却下した事例。
(東京高決昭55・3・21判タ417・154)
○親権者である母及び養父が子を養育監護しておらず、今後も必要な養育監護をする意思が認められないこと、正当な理由もなく医療行為に同意しないため、子が検査を受けたり通院することが困難な状況にあること等から、母及び養父の親権を2年間停止した事例。
(宮崎家審平25・3・29家月65・6・115)
○親権停止の審判後、再婚し安定した家庭生活に入っていること、子も親権者と再婚相手を信頼し、両名らと生活することを望んでいること、児童相談所も審判の取消しを支持していることなどを理由に、親権停止の審判が取り消された事例。
(和歌山家審平27・9・30判時2310・132)
○裁判上の離婚の場合に裁判所が父母の一方を親権者と定める民法819条2項の規定が、憲法13条・14条1項・24条2項又は日本が批准した条約に違反するとして、それを改廃する立法措置をとらない立法不作為を理由とした国家賠償請求に対し、それらの違反が明白であるとは認められないとして、これを棄却した事例。
(東京地判令3・2・17(平31(ワ)7514))